委員長メッセージ立教大学大学院 社会デザイン研究科
困難と混乱の時代の社会デザイン学への招待
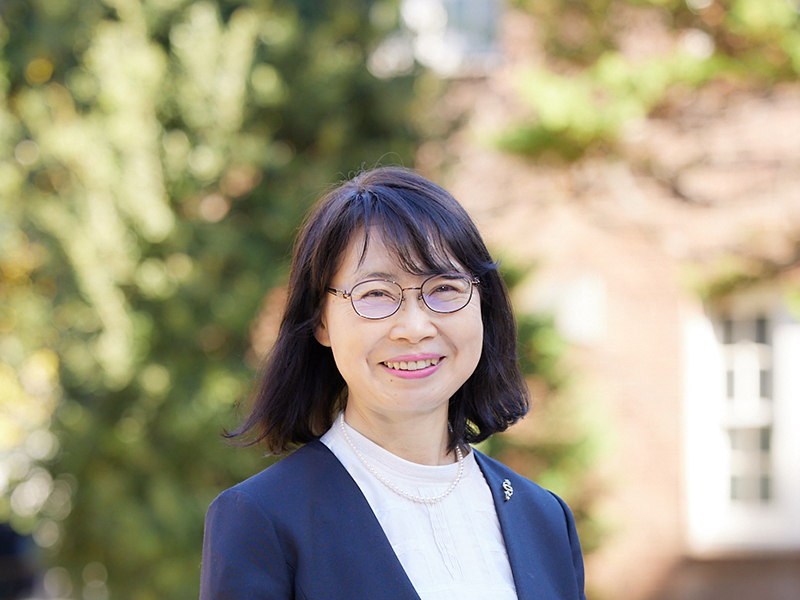
二つの世界大戦を経験し,「戦争の世紀」「難民の世紀」と呼ばれた20世紀に別れを告げ,希望と期待をもって迎えらえたミレニアム・21世紀は,米国同時多発テロという,新たな形の「戦争」とともに幕を開けました。立教大学21世紀社会デザイン研究科(現,社会デザイン研究科)が,「ネットワーク」,「非営利組織の経営」そして「危機管理」を研究教育上のキーワードとして,非営利・公共分野にかかわる組織の運営・経営人材を輩出する日本初のビジネススクールとして設立されたのは,翌2002年4月のことです。
以来20年,前世紀からの宿題・積み残しに加え,あらゆる次元での分断・対立が一層先鋭化し,地球環境は,「人新生(ひとしんせい・Anthropocene)」という新しい時代区分が登場するほどに,人間の活動により大きく変化,未曽有の自然災害が世界各地を襲う時代に突入しています。「気候正義(climate justice)/環境正義(environmental justice)」という言葉が,まさにこの時代を象徴しています。
同時に,本来であれば世界が一丸となって,人間が生み出した,この地球環境問題への対応に全力を尽くしていかねばならない時代に,世界は,というより,人間は,言葉を失うような戦争,紛争,人道危機を引き起こしてしまっています。
しかし,だからこそ,私たちが20年にわたって追求してきた「社会デザイン」が必要とされる時代であると感じます。私たち社会デザイン研究科は,多様で異なる価値観を持つ人々が共生していくための知恵や仕掛けを社会と捉え,そこでの人々の参加・参画の仕方を,従来の常識にとらわれず,大胆に組み替え,革新(イノベーション)していく思考と実践を重ねてきました。
この思考と実践の過程で,私たちが重視し,研究科の知的営為の根底に据えてきたものが,領域横断的かつ,分断・対立を超越する思考・思想と,セクターの垣根を越えた「協働」,学問の基礎を固めた上で全体を俯瞰する「鳥の目」,そして地域や生活といった足元,根元からの人びとの営みを重視し,様々な領域の具体的課題に対するアプローチをはぐくむ「虫の目」です。私たちが目指すのは,夢や理想を現実のものにするために,果敢に挑戦し,あきらめずに格闘してきた人々の多様な経験を「継承」し,先人たちが築き,担ってきた歴史を踏襲しつつ,新たな方法論と表現を獲得していくこと,やむにやまれぬ思いから立てた「問い」や課題の解決へ向け,変革を現実のものにしていくこと,その実現のために粘り強いプロセスを歩むことです。そのための理論的・構造的な探究はもとより,現場と往復し,当事者性と内発性をそなえた実践的な研究を私たちは歓迎します。
では皆さんが学ぶ「社会デザイン学」とは何でしょう。私たち社会デザイン研究科が考える社会デザイン学とは,
《格差や排除,分断・対立が先鋭化し,地球環境に過度な負担を強いる現代社会にあって,組織や制度,文化,技術などの巨視的な視座を持ちながらも,システムに還元し得ない多様性,当事者性,生の一回性という小さな,個別具体的な物語に共感しつつ,対話を促進し,架け橋となり,持続可能な共生社会を再構築又は創成するための思考と実践の学》
これを短く端的にまとめるなら,《多様性に富んだ,持続可能な共生社会を創成するために必要な思考と実践に関する学》です。
皆さんにとって,社会デザイン研究科は,おそらく他に類をみない「出会い」の場になるはずです。教員とのやりとりや院生同士の関わりあいのなかから,決して単純な知識やスキルの獲得にとどまることのない実践的研究力と新たな職能とを,自らのうちにぜひ育てていただきたいと思っています。
社会デザイン学の世界へようこそ。混迷の時代に,社会デザイン学の地平をともに開いていきましょう。
社会デザイン研究科委員長 長 有紀枝
以来20年,前世紀からの宿題・積み残しに加え,あらゆる次元での分断・対立が一層先鋭化し,地球環境は,「人新生(ひとしんせい・Anthropocene)」という新しい時代区分が登場するほどに,人間の活動により大きく変化,未曽有の自然災害が世界各地を襲う時代に突入しています。「気候正義(climate justice)/環境正義(environmental justice)」という言葉が,まさにこの時代を象徴しています。
同時に,本来であれば世界が一丸となって,人間が生み出した,この地球環境問題への対応に全力を尽くしていかねばならない時代に,世界は,というより,人間は,言葉を失うような戦争,紛争,人道危機を引き起こしてしまっています。
しかし,だからこそ,私たちが20年にわたって追求してきた「社会デザイン」が必要とされる時代であると感じます。私たち社会デザイン研究科は,多様で異なる価値観を持つ人々が共生していくための知恵や仕掛けを社会と捉え,そこでの人々の参加・参画の仕方を,従来の常識にとらわれず,大胆に組み替え,革新(イノベーション)していく思考と実践を重ねてきました。
この思考と実践の過程で,私たちが重視し,研究科の知的営為の根底に据えてきたものが,領域横断的かつ,分断・対立を超越する思考・思想と,セクターの垣根を越えた「協働」,学問の基礎を固めた上で全体を俯瞰する「鳥の目」,そして地域や生活といった足元,根元からの人びとの営みを重視し,様々な領域の具体的課題に対するアプローチをはぐくむ「虫の目」です。私たちが目指すのは,夢や理想を現実のものにするために,果敢に挑戦し,あきらめずに格闘してきた人々の多様な経験を「継承」し,先人たちが築き,担ってきた歴史を踏襲しつつ,新たな方法論と表現を獲得していくこと,やむにやまれぬ思いから立てた「問い」や課題の解決へ向け,変革を現実のものにしていくこと,その実現のために粘り強いプロセスを歩むことです。そのための理論的・構造的な探究はもとより,現場と往復し,当事者性と内発性をそなえた実践的な研究を私たちは歓迎します。
では皆さんが学ぶ「社会デザイン学」とは何でしょう。私たち社会デザイン研究科が考える社会デザイン学とは,
《格差や排除,分断・対立が先鋭化し,地球環境に過度な負担を強いる現代社会にあって,組織や制度,文化,技術などの巨視的な視座を持ちながらも,システムに還元し得ない多様性,当事者性,生の一回性という小さな,個別具体的な物語に共感しつつ,対話を促進し,架け橋となり,持続可能な共生社会を再構築又は創成するための思考と実践の学》
これを短く端的にまとめるなら,《多様性に富んだ,持続可能な共生社会を創成するために必要な思考と実践に関する学》です。
皆さんにとって,社会デザイン研究科は,おそらく他に類をみない「出会い」の場になるはずです。教員とのやりとりや院生同士の関わりあいのなかから,決して単純な知識やスキルの獲得にとどまることのない実践的研究力と新たな職能とを,自らのうちにぜひ育てていただきたいと思っています。
社会デザイン学の世界へようこそ。混迷の時代に,社会デザイン学の地平をともに開いていきましょう。
社会デザイン研究科委員長 長 有紀枝
